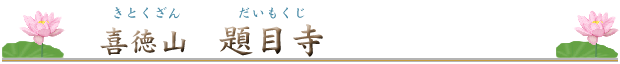
お問い合わせなど
沿革
寛政年間(1789~1801)の創立。開基日観(題目教会、大坊顕の字法縁)。善慶院日具(喜徳教会、潮師法縁)。
題目教会は寛政年間に日観が題目堂を鈴ケ森刑場近くに建立、文政7年に本堂を建立した。天保の改革で廃寺となったが、後に再びその地に小庵を建立。喜徳教会は明治40年に身延山流祈祷修法の道場として、大森に開設された。昭和47年に両教会を合併し寺号を公称した。刑死者の供養塔(髑髏塚)があった。
題目寺にあった祖師像は区の文化財級の立派なものであったが、これは宮中大奥の女中が約20名連署して、鈴ケ森の刑場で処刑された人々の供養のために造立したもので、戦争中は大坊本行寺に疎開して戦火を免れ、題目寺崩壊後は一時佐世保の本興寺に安置され、その後大阪に移されたと聞く。
平成14年10月長崎県西彼杵郡の喜徳教会が寺号公称して題目寺となる。住職は岳野宣延師。
題目教会は寛政年間に日観が題目堂を鈴ケ森刑場近くに建立、文政7年に本堂を建立した。天保の改革で廃寺となったが、後に再びその地に小庵を建立。喜徳教会は明治40年に身延山流祈祷修法の道場として、大森に開設された。昭和47年に両教会を合併し寺号を公称した。刑死者の供養塔(髑髏塚)があった。
題目寺にあった祖師像は区の文化財級の立派なものであったが、これは宮中大奥の女中が約20名連署して、鈴ケ森の刑場で処刑された人々の供養のために造立したもので、戦争中は大坊本行寺に疎開して戦火を免れ、題目寺崩壊後は一時佐世保の本興寺に安置され、その後大阪に移されたと聞く。
平成14年10月長崎県西彼杵郡の喜徳教会が寺号公称して題目寺となる。住職は岳野宣延師。
