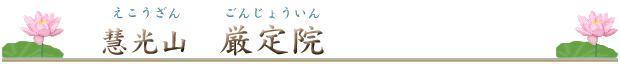
- 【住職名】
- 43世 小黒英真
- 【旧称】
- 成就坊→厳成坊
- 【旧本寺名】
- 池上本門寺
- 【旧寺格】
- 平 池上・大坊顕の字法縁
- 【本尊勧請様式】
- 大曼荼羅一塔両尊四士
- 【祖像】
- 説法像(昭和56年、宗祖700遠忌に野坂法山師によって製作された)。 本堂に奉安されていた祖師像(享保5=1720年の作で寄木造)は別院である鬼子母神堂に遷座。
- 【仏像】
- 持国天王立像(昭和初期) 毘沙門天立像(昭和初期) 鬼子母神立像・十羅刹女立像(江戸期) 鬼子母神立像(安産子安守護・大正9年) 釈迦多宝如来像(昭和初期) 四菩薩立像(昭和初期) 普賢菩薩騎像(昭和期) 能勢妙見像(昭和初期) 八大竜王立像(昭和初期) 最上稲荷坐像(昭和初期) 七面大明神坐像(昭和44年)
- 【寺宝】
- 大黒天版木(江戸期) 観音像(人間国宝・円鍔勝三作三十三観音の中の一体) 打出の小槌2個題目板碑(宝徳3年=1451) 絵画「雨後の山(横山大観画伯)
お問い合わせなど
- 【所在地】
- 〒146-0082 大田区池上2-10-12
- 【電話】
- 03-3751-6767
沿革
正応2年(1289)の創立。開基厳定院日尊。
開基檀越高梨正徳。開基檀越の一子で、六老僧大国阿闍梨日朗の弟子隆王麿、後の成就坊日尊が創建したことから、はじめ成就坊と呼ばれた。天文五年に厳完院と合併したと伝えられるが (古書には厳成院とある)、詳細は明らかでない。
厳定院の初代は厳定院日尊上人(天文五=1536年三月遷化)、中興21世禅定院日逞上人(享保3=1723年遷化)。40世久成院日芳上人は昭和6年(1937)に別院として常仙院隣に鬼子母神堂を開堂。本堂は昭和8年に再建。池上七福神の弁財天をまつる。平成15年、立教開宗750年慶讃事業として本堂屋根を鋼板本葺にて葺替、客殿新築に着手。
平成15年立教開宗750年慶讃事業として本堂屋根銅板葺替えならびに本堂基礎耐震工事完成。更に客殿庫裡改築工事を発願し平成17年6月完成する。
開基檀越高梨正徳。開基檀越の一子で、六老僧大国阿闍梨日朗の弟子隆王麿、後の成就坊日尊が創建したことから、はじめ成就坊と呼ばれた。天文五年に厳完院と合併したと伝えられるが (古書には厳成院とある)、詳細は明らかでない。
厳定院の初代は厳定院日尊上人(天文五=1536年三月遷化)、中興21世禅定院日逞上人(享保3=1723年遷化)。40世久成院日芳上人は昭和6年(1937)に別院として常仙院隣に鬼子母神堂を開堂。本堂は昭和8年に再建。池上七福神の弁財天をまつる。平成15年、立教開宗750年慶讃事業として本堂屋根を鋼板本葺にて葺替、客殿新築に着手。
平成15年立教開宗750年慶讃事業として本堂屋根銅板葺替えならびに本堂基礎耐震工事完成。更に客殿庫裡改築工事を発願し平成17年6月完成する。
定期行事
| 行事内容 | 日時 | 対象など |
|---|---|---|
| 春季彼岸会 | 中日 | |
| 盂蘭盆施餓鬼会 | 7月8日 | |
| 秋季彼岸会 | 中日 | |
| 新春祈祷会 | 1月5日 |
紹介動画
寺院データ
| 供養内容 | 日時、お申し込みなど |
|---|---|
| 塔婆供養 | 要問合せ |
| 永代供養 | 要問合せ |
| 供養内容 | 日時、お申し込みなど |
|---|---|
| 年間祈願 | 要問合せ |
| 交通安全 | 要問合せ |
| 七五三 | 要問合せ |
| 地鎮祭 | 要問合せ |
| 家祈祷 | 要問合せ |
| 厄除け | 要問合せ |
| 施設 | お申し込みなど |
|---|---|
| 分譲墓地 | 要問合せ |
| 葬儀会館 | 要問合せ(エコーホール) |
| 永代供養塔 | 要問合せ |



