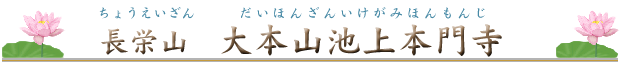
- 【住職名】
- 83世 菅野日彰
- 【院号】
- 大国院
- 【旧本寺名】
- 大本山
- 【本尊勧請様式】
- 一尊四士像(本殿奉安) 昭和44(1969)年
- 【祖像】
- 木造(大堂奉安)国重文・正応1年(1288)
- 【仏像】
- 木造日朗坐像(大堂安置) 木造日輪坐像(大堂安置) 木造釈迦牟尼仏像(本殿安置・阿井瑞 岑作) 四菩薩像(本殿安置・野坂法山他三名作・昭和44年) 一塔両尊坐像(江戸初期・五重塔安置) 木造四菩薩立像(江戸初期・五重塔安置) 鋳像釈迦坐像(享保13年・常経殿安置) 木造長栄天立像(長栄堂安置) 大黒天像(長栄堂安置) 木造日朝立像(日朝堂安置)
- 【寺宝】
- 曼荼羅 宗祖自筆(弘安4年=1281) 池上2世日朗・3世日輪・7世日寿・8世日調・9世日純・11世日現・12世日惺・13世日尊・14世日詔・復歴16世日樹・16世日遠・17世日東・22世日玄・26世日芳・28世日侃・33世日謙 身延20世日重・21世日乾・25世日深・油屋日珖・深草元政法資慧明院日燈等
古文書 宗祖御真筆 - 兄弟鈔 報恩鈔 弁殿御消息 富木尼御前御返事 下山御消息 妙法尼御前御消息等
お問い合わせなど
- 【所在地】
- 〒146-8576 大田区池上1-1-1
- 【電話】
- 03-3752-2331
- 【ホームページ】
- http://honmonji.jp
沿革
宗祖入滅の霊地にして、古来身延山久遠寺・中山法華経寺と共に三頭、また長興山妙本寺及び長谷山本土寺と共に三長三本と称せられた。
宗祖は弘安5年10月13日、池上宗仲の邸(現在の大坊本行寺)で入滅。
本門寺の開創に関しては諸説あるが、池上家邸内の持仏堂が法華堂になった(今の大坊本行寺)のが建治2年(1276)であり、のちに山上(今の本門寺)に一宇が建立され、宗祖が弘安5年(1282)9月に開堂供養を御親修になり、長栄山本門寺と御命名遊ばしたと伝える。
宗祖在世時に既に堂宇の建立がなされ、池上宗仲の寄進により六万九千三八四坪が寺領となり、直弟日朗に継承され、日朗の阿闍梨号に因んで大国院とも称した。池上・比企両山(池上本門寺と比企谷妙本寺 は、両山一貫首の制度によって、代々運営されてきたが、江戸幕府が開かれてからは、比企谷に司務職を置き、貫首は池上本門寺に常住するようになった。なお、この制度は昭和16年に廃止された。
昭和20年4月15日の空襲で五重塔・経蔵・宝塔・総門を除く56棟約二五〇〇坪の建物が焼失。昭和23年(1948)祖廟・仮祖師堂再建。昭和28年奉安塔・中庸館、昭和29年書院・方丈が完成。昭和39年大堂(祖師堂)・侍曹寮再建。昭和41年体育館、昭和42年大堂天水桶、朗尊650遠忌記念として昭和44年に本殿・常経殿・朗峰会館・大廻廊・大玄関、昭和46年に水屋完成。宗祖700遠忌記念として昭和52年に仁王門・仁王尊像、昭和53年に書院・庫裡・随身寮、昭和54年に御廟所等を完成。
平成10年3月、立教開宗750年慶讃事業として、五重塔の解体大修理、霊宝殿新築、大堂大改修、新調仁王尊像造立に着手。平成14年4月3日より4月7日まで5日間に亘り立教開宗750年慶讃事業落慶法要が奉行された。
宗祖は弘安5年10月13日、池上宗仲の邸(現在の大坊本行寺)で入滅。
本門寺の開創に関しては諸説あるが、池上家邸内の持仏堂が法華堂になった(今の大坊本行寺)のが建治2年(1276)であり、のちに山上(今の本門寺)に一宇が建立され、宗祖が弘安5年(1282)9月に開堂供養を御親修になり、長栄山本門寺と御命名遊ばしたと伝える。
宗祖在世時に既に堂宇の建立がなされ、池上宗仲の寄進により六万九千三八四坪が寺領となり、直弟日朗に継承され、日朗の阿闍梨号に因んで大国院とも称した。池上・比企両山(池上本門寺と比企谷妙本寺 は、両山一貫首の制度によって、代々運営されてきたが、江戸幕府が開かれてからは、比企谷に司務職を置き、貫首は池上本門寺に常住するようになった。なお、この制度は昭和16年に廃止された。
昭和20年4月15日の空襲で五重塔・経蔵・宝塔・総門を除く56棟約二五〇〇坪の建物が焼失。昭和23年(1948)祖廟・仮祖師堂再建。昭和28年奉安塔・中庸館、昭和29年書院・方丈が完成。昭和39年大堂(祖師堂)・侍曹寮再建。昭和41年体育館、昭和42年大堂天水桶、朗尊650遠忌記念として昭和44年に本殿・常経殿・朗峰会館・大廻廊・大玄関、昭和46年に水屋完成。宗祖700遠忌記念として昭和52年に仁王門・仁王尊像、昭和53年に書院・庫裡・随身寮、昭和54年に御廟所等を完成。
平成10年3月、立教開宗750年慶讃事業として、五重塔の解体大修理、霊宝殿新築、大堂大改修、新調仁王尊像造立に着手。平成14年4月3日より4月7日まで5日間に亘り立教開宗750年慶讃事業落慶法要が奉行された。
信行会・行事
- 毎月様々な行事が開催されています。詳しくはホームページをごらんください。
定期行事
| 行事内容 | 日時 | 対象など |
|---|---|---|
| 春季彼岸会 | 春分の日 | 檀信徒のみ |
| 花まつり | 4月第一土日 | どなたでも可 |
| 盂蘭盆施餓鬼会 | 7月7日 | 檀信徒のみ |
| 秋季彼岸会 | 秋分の日 | 檀信徒のみ |
| 宗祖御報恩会式 | 10月11〜13日 | どなたでも可 |
| 除夜会 | 12月31日 | どなたでも可 歳末読経 |
| 新春祈祷会 | 元日〜3日 | どなたでも可 交通安全祈祷も行っています。 |
| 節分会 | 2月3日 | どなたでも可 |
紹介動画
寺院データ
| 供養内容 | 日時、お申し込みなど |
|---|---|
| 塔婆供養 | 要問合せ |
| 水子供養 | 要問合せ |
| 永代供養 | 要問合せ |
| 供養内容 | 日時、お申し込みなど |
|---|---|
| 交通安全 | 10時〜14時半、どなたでも可 於:大堂 |
| 七五三 | 10月下旬〜11月下旬、 どなたでも可 於:大堂 |
| 地鎮祭 | 要問合せ |
| 家祈祷 | 要問合せ |
| 厄除け | 10時〜15時、 どなたでも可 於:大堂 |
| 虫出し虫封じ | 要問合せ 於:長榮堂 |
| 施設 | お申し込みなど |
|---|---|
| 分譲墓地 | 要問合せ(檀家のみ) |
| 永代供養塔 | 要問合せ(檀家のみ) |
見どころ
- 春には桜が咲きます。また、10月12日の宗祖御逮夜の折には万灯練り供養が行われます。
史跡、文化財など
- 日蓮聖人真筆本尊 日朗、日輪等歴代上人本尊「兄弟抄」(重文)他多数
- 日蓮聖人御尊像(重文)、五重塔(重文)、多宝塔(重文)など











