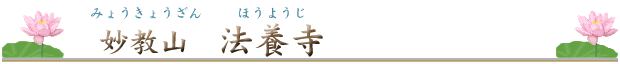
- 【住職名】
- 27世 木村中一
- 【旧本寺名】
- 池上本門寺
- 【旧寺格】
- 紫 小西法縁
- 【本尊勧請様式】
- 一塔両尊四士 (徳川四代家綱室寄進)
- 【祖像】
- 説法像(江戸城本丸安置のものを家綱寄進・鎌倉時代末)
- 【仏像】
- 四天王像(徳川家綱室寄進) 子安妙見大菩薩(琢磨法眼作) 大黒天(徳川8代吉宗寄進) 鬼子母神 熊谷稲荷大明神(元禄15年開眼)
- 【寺宝】
- 伝宗祖本尊(建治2年) 中山日祐・池上12世・16世・23世・26世・29世・30世・47世・55世・60世・身延24世・33世本尊 釈迦涅槃図繍仏 豊臣秀吉朱印状 小西檀林説法免許状 比企谷再建
御開帳一件許状 大奥局書状 その他縁起・書跡・絵画・板碑等
お問い合わせなど
- 【所在地】
- 〒146-0082 大田区池上1-19-25
- 【電話】
- 03-3751-6728
沿革
天正15年(1587)頃、神田三河町に創立。開山妙経院日等。
慶長年間に下谷稲荷町へ移転、江戸城両御丸と大奥の祈祷所となり「わら店の法養寺」と呼ばれた。
稲荷町時代から境内に祀られた「熊谷稲荷」(伝教大師の一之守と書いたものが腹蔵されていたと伝えられる)は江戸市中の信仰を集めた。
明治43年に池上妙教庵を合併、池上へ移転。山号勧明山を妙教山と改めた。
妙教庵は今の法養寺域にあった蓮光院の旧地に9代将軍徳川家重の尊体安泰を念じて出家した妙教比丘尼(清信院妙教日理尼)が寛保3年(1743)に庵室を再興、貫首日芳から庵号を授与されたものである。
釈迦涅槃図繍仏は寛文3年(1663)縫物師戸塚七兵衛によって制作されたものである。釈迦入滅の様子を総刺繍で表し、仏画と比較しても立派な物である。緑、紫、青、白の色調の絹平糸で人物、動物、昆虫に至るまで嘆き悲しむ表情が詳細に描写されている特に釈迦の体躯は金撚糸で駒繍されている。螺髪の渦巻には紀州藩2代光貞の妻天真院が自身の前髪を繍い込めたもので、当時浅草にあった勧明山法養寺に寄進されたものである(平成15年「大日蓮展」協力)。
13世日慥は小室妙法寺37世へ。
慶長年間に下谷稲荷町へ移転、江戸城両御丸と大奥の祈祷所となり「わら店の法養寺」と呼ばれた。
稲荷町時代から境内に祀られた「熊谷稲荷」(伝教大師の一之守と書いたものが腹蔵されていたと伝えられる)は江戸市中の信仰を集めた。
明治43年に池上妙教庵を合併、池上へ移転。山号勧明山を妙教山と改めた。
妙教庵は今の法養寺域にあった蓮光院の旧地に9代将軍徳川家重の尊体安泰を念じて出家した妙教比丘尼(清信院妙教日理尼)が寛保3年(1743)に庵室を再興、貫首日芳から庵号を授与されたものである。
釈迦涅槃図繍仏は寛文3年(1663)縫物師戸塚七兵衛によって制作されたものである。釈迦入滅の様子を総刺繍で表し、仏画と比較しても立派な物である。緑、紫、青、白の色調の絹平糸で人物、動物、昆虫に至るまで嘆き悲しむ表情が詳細に描写されている特に釈迦の体躯は金撚糸で駒繍されている。螺髪の渦巻には紀州藩2代光貞の妻天真院が自身の前髪を繍い込めたもので、当時浅草にあった勧明山法養寺に寄進されたものである(平成15年「大日蓮展」協力)。
13世日慥は小室妙法寺37世へ。
定期行事
| 行事内容 | 日時 | 対象など |
|---|---|---|
| 春季彼岸会 | 春分の日 | 檀信徒のみ |
| 花まつり | 4月8日 | 檀信徒のみ |
| 盂蘭盆施餓鬼会 | 7月20日 | 檀信徒のみ |
| 秋季彼岸会 | 秋分の日 | 檀信徒のみ |
| 宗祖御報恩会式 | 10月13日 | 檀信徒のみ |
紹介動画
寺院データ
| 供養内容 | 日時、お申し込みなど |
|---|---|
| 塔婆供養 | 当山信徒 |
| 永代供養 | 当山信徒 |
| 施設 | お申し込みなど |
|---|---|
| 分譲墓地 | 未信徒は当山信徒となる |
| 永代供養塔 | 未信徒は当山信徒となる |
見どころ
- 春のしだれ桜をはじめ、四季折々の境内の花々が参拝者の心を癒してくれます。
史跡、文化財など
- 祖師像・釈尊涅槃図が大田区文化財(非公開)



